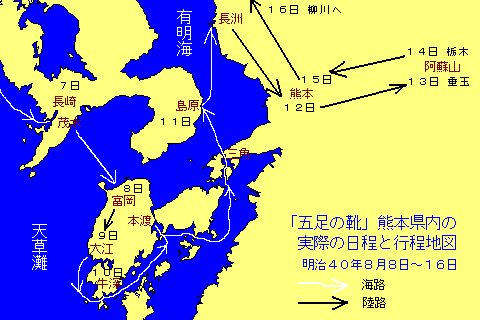
| 明治40年夏、与謝野鉄幹ら5人の九州旅行記「五足の靴」が東京二六新聞に連載されます。その中から熊本県内に関する部分を、五足の靴研究家であられる濱名志松先生の著書「五足の靴と熊本・天草」(国書刊行会発行)より紹介させていただきます。なお、日付は新聞連載の日付であり、実際に旅をした日付とは異なります。一行が長崎県茂木(もぎ)港から天草の富岡港に上陸した実際の日付は8月8日です。 |
|---|
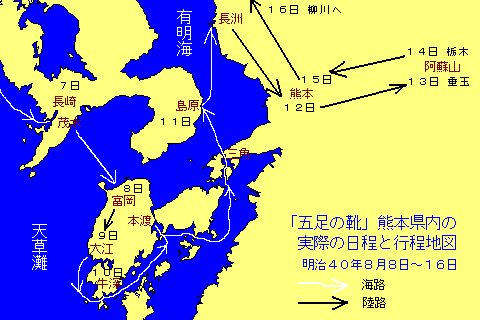 |
荒れの日 (八月十九日)
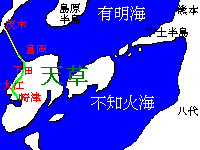 風は朝となって愈々(いよいよ)激しくなった。長崎港には灰色の波が騒いで居る。折々沛然(はいぜん)たる驟雨(しゅうう)がやってきて長崎を流さうとする。 風は朝となって愈々(いよいよ)激しくなった。長崎港には灰色の波が騒いで居る。折々沛然(はいぜん)たる驟雨(しゅうう)がやってきて長崎を流さうとする。赤玉は依然として竿頭にぶら下がって怖れの象徴となる。船が出ればよいがと心配したが、その内に大分和らぎ、日も出たから兎も角もとて乗合馬車の窮屈を忍び二里の山路を茂木へ向った。茂木は率土の浜である。干潮で水涸れの川が橋を境に海に通ず橋の上には鶩(あひる)が数十泳いでゐる。橋の下なる海には黒い子供が数十泳いでゐる、同じ様である。風がある。小汽船が二艘(そう)棧橋に繋がれてゐる。乱雑、活動の港長崎と比べると隔世の感がある。その一に乗った。十一時出帆、天草諸港へ行く船である。相変わらず後甲板を占領す。ボーイが来て下へ入れといふ、此の暴風(しけ)では甲板は波が被ると脅す、沖を見るとどす黒い中に白波が見える。風は山に鳴る、B生は驚いて下に逃げ込んだが、後の四人は甲板に残る。 軈(やが)て笛が鳴って機関が働き出すと直ぐ揺れ初めた。下の船室には男女十四人、五人ごろごろと芋の様に寝てゐる。昨日もいい加減ひどかったが今日のはまだまだひどい、昨夜なども山の窪へと船を入れて寝てゐると、此方(こっち)から彼方(あっち)へころころ転がるが、転がるのはいいが柱へ頭をぶっつけて寝られたものぢやなかったとボーイがいふ。円い小さい眼のような窓の穴も波が入るとて閉めて仕舞った。風の故か左程蒸熱くもない。小さな船は常さへも荒れるといふ千々岩(ちちいは)灘を此(この)荒の日に横ぎらうとする。行くに従って海は愈々(いよいよ)荒れ、白い毛を頭に被(かつ)いだ怪物が海を埋め、己れ小癪(こしゃく)と船をめがけて八方からひしひしと攻めかかる。船は思ふが儘(まま)に弄(もてあそ)ばれる。思へば船も亦怪物である。鯨の一種である。頭もある、尾もある、腹も背もある、さう思へば眼もある、鰯(いわし)の代りに石炭を呑み、潮の代りに烟(けむり)を吐く。ひらひらと弄ばれながらも驀(まっしぐら)に進んでめく。風がざあざあとなると波がどどどおと答へる。空には灰色の雲がまだらに散って荒れ狂う怪物に応援して居る。何しろ痛い暴風(しけ)だ。斯(か)くとは初めから分かってゐたのに、今更不平もいへぬ。頭を上げれば酔う、眼を開ければ酔う、体を動かせば酔う。横に寝て、自分を一個の物と見做(みな)して、波のまにまに運動するに限る。酔いやあ仕まいかなどと思ってはならん。すうっと昇る時は体が船にどしんと中(あた)る、どうつと降る時は体がふわりと浮く、いい気持だが、又いやな気持である。左右に揺れるとごろごろと転がる。B生は船室にあって廻りでがあがあ物を吐く声を紛らす為に全二時間口を衝いて出る限りの歌を繰り返して歌って居る、後甲板ではM生がこれものべつに鼻唄を歌ふ、K生はころころと転んで危ふく波に陥(おち)いらむとした、I生は黙して眠る、茲(ここ)に唯一人H生は勇を鼓して起きてゐた、猛り狂ふ濤(なみ)を快しと眺めしや否やは知らぬ、兼ねてボーイの喧嘩の仲裁者であったそうな。僅(わず)かに後の方一部を残して甲板はざっと許りに波に洗はれて居る。曇れる日は晴れさうにない。斯(こ)の如くして時が進んで向こうに天草が見え、軈(やが)て内海に入ると波は次第に静まった。もう大丈夫、甲板へ出てもとボーイが得意になって触れ廻る。人はやっと蘇生した。波静かなる富岡港に上陸した。細長い小半島の終点に富岡城の趾がある、細長い町を挾んで西は外界の波が荒れている、東は嘘のように平な内海である。町長松本氏から天草の乱に関する諸々の事を聞く。話の序に、ピヤアロンの事が出た。美しく飾られた幾艘(そう)の船が更に幾十艘(そう)の小船の勢援の下に行ふ支那流のレガッタであるさうな、普通五月の節句にやるのだといふ。天草の乱の時独り此の城が陥らなかったといふ様な話を聞いた。又武田氏の蔵書「天草記録」と云ふ写本を読んだ。 |
蛇と蟇 (八月二十日)
 富岡より八里の道を大江に向ふ。難道だと聞いた。天草島の西海岸を北より南へ、外海の波が噛みつくがりがりの石多き径に足を悩ましつつ行くのである。土痩せたる天草の島は稲を作るのに適せぬ、山の半腹の余裕なき余裕を求めて甘藷(かんしょ)を植ゑる。島民は三食とも甘藷を食ふ。或る処は川が路である、点々たる石を伝ふて辛うじて進む。その多くは塁々として砂礫(されき)尽くるなり荒礫左に聳(そばだ)つ嶮山(けんざん)の裾(すそ)を伝ふて行く。足早き人K生M生はずんずん先へ行く、目的はパアテルさんを訪(おとな)うにある。足遅き人I生H生B生は休み休みゆっくり後から来る、目的は言うが如くんば歴史にあらず、考証に非ず、親しく途上に自然人事を見聞するにある。大岩に罅(ひび)が入り象形文字の様に見ゆる断崖のもとを廻る処で紛(はぐ)れてしまった。顧みれば淡く霞んで富岡半島がまだ見えた。三里か四里は来たらう。茶屋の婆(ばゝあ)に婆さんの言葉はちっとも分らぬと言ふと、あんたがたの云はっしゃる事も分かりまっせんと言った。婆さん子供があるかい。ありますとも。幾つだい。幾つだって大勢居るさあ。爺さんは居るのかね、爺さん居らつさんば、一寸(ちっとん)楽しみも無かとで御座いますたい。とやったので皆吹出してしまった。歯抜け婆さんの愛嬌のある事よ。 富岡より八里の道を大江に向ふ。難道だと聞いた。天草島の西海岸を北より南へ、外海の波が噛みつくがりがりの石多き径に足を悩ましつつ行くのである。土痩せたる天草の島は稲を作るのに適せぬ、山の半腹の余裕なき余裕を求めて甘藷(かんしょ)を植ゑる。島民は三食とも甘藷を食ふ。或る処は川が路である、点々たる石を伝ふて辛うじて進む。その多くは塁々として砂礫(されき)尽くるなり荒礫左に聳(そばだ)つ嶮山(けんざん)の裾(すそ)を伝ふて行く。足早き人K生M生はずんずん先へ行く、目的はパアテルさんを訪(おとな)うにある。足遅き人I生H生B生は休み休みゆっくり後から来る、目的は言うが如くんば歴史にあらず、考証に非ず、親しく途上に自然人事を見聞するにある。大岩に罅(ひび)が入り象形文字の様に見ゆる断崖のもとを廻る処で紛(はぐ)れてしまった。顧みれば淡く霞んで富岡半島がまだ見えた。三里か四里は来たらう。茶屋の婆(ばゝあ)に婆さんの言葉はちっとも分らぬと言ふと、あんたがたの云はっしゃる事も分かりまっせんと言った。婆さん子供があるかい。ありますとも。幾つだい。幾つだって大勢居るさあ。爺さんは居るのかね、爺さん居らつさんば、一寸(ちっとん)楽しみも無かとで御座いますたい。とやったので皆吹出してしまった。歯抜け婆さんの愛嬌のある事よ。暫く行くと先に立ったH生がぴたりと止まった。五尺余りの大かがち、紅き地に黒き斑(まだら)を物凄く染め出した縞蛇(しまへび)が犬の頭ほどの蟇(がま)を呑みかけてゐる。岸を打つ波の音は白い、山を吹く風は青い、その間を縫う径の中央で蛇が蟇を飲む。三生暫くは呆れて眼を見張って突立った。人ありと知るや知らずや、蛇は長き体をうねうねとうねらせて草の中へ引きずり込もうとする、蛙は弱いが重い、前足の一つを噛(か)ませて硬く執って動かぬ、或は既に死んだのか知れん。強者弱者を食ふ比ぶるものなき残忍なる行為だ。自然の一部には眦(まなじり)をさいて呪ふべきものがある。やはか許すべきと路傍の大石を空高く振り翳(かざ)したるI生は近(ちかづ)いた。やっと言ふと蛇は砕けた、と思ひの外どうも無い、打たれて痛かったのか暫くは動かぬ、今度は赤い舌をぺろぺろ吐いた、吐いた舌を従順なる蟇の背に向け食ひついた、くわっと怒ったI生は此(この)時他の石を拾った、今度はと思ったが失策(しくじ)った、中(あた)つたが死なぬ、するすると伸びて叢(くさむら)へ逃げ込んだ、そら来たと言ってI生は海の方へ逃げ出した、B生もあわてて逃げ出した、H生は後の始末を見届けて、何れも波打際に転がって居る石を渡って行く事にした。途に小さい炭鉱があった、古ぼけたボイラーが破れた家根の下で燻(いぶ)って居る。山を腹に穴を明けて石炭をえぐり出す、奥を見ると真暗な穴の入り口に裸の男が暑さうに寝ていた。 暫く行くと道は山へ登る、羊歯(しだ)が青々と一面に繁って暖き南の国の香を送る。脚下の白い波をたどると水平線が大分高まって居る。杉の木立が黒ずんで山麓を飾る、その間から紺碧の海が見え、涼しい風が吹く。汗は背、腹を洗ひ、頭から流れるものは眉を溢れて頬に伝ふ。水あれば水を飲み、茶あれば茶を呼ぶ、今朝から平均一人五升も飲んだか、腹がだぶだぶする、胃はもう沢山だといふ。喉はもっと欲しいと促す、勝は常に喉に帰した。山の方が道は楽である。峠を越す事二つ三つにして下津深江といふ湯の出る港へ着いた。午後二時。先着のK生M生が待って居た。農事講習会の災する処となって茶屋も宿屋も断られ、大いに困って此処(ここ)へ頼んだといふ、瀟洒(しょうしゃ)なる物売る家の二階に通る。老主人来る、頗(すこぶ)る慇懃(いんぎん)である。一体この辺の言葉はとんと素人には分らぬ、それかあらぬか、老人は気を利かして一切土語(どご)を語らぬ。「君達は」と口を開いた、これは最上の敬称代名詞の積りと見える。「いづ方へ参られまするか。」又言ふ「道は甚(はなは)だ険道(けんどう)でありまするとは雖(いえど)も。」又言ふ「必ず似て参られまする、は、は。」その代わりよく分った。梅干しも奈良漬も皆甘かった。一睡して、大江迄もう四里、訳はないと、三時を過ぐる幾分に出かけた。 |
大失敗 (八月二十一日)
 五足の靴は驚いた。東京を出て、汽車に乗せられ、唯(ただ)僅(わずか)に領巾振山(ひれふるやま)で土の香を嗅(か)いだのみで、今日まで日を暮したのであった、初めて御役に立って嬉しいが、嬉しすぎて少し腹の皮を擦りむいた、いい加減に御免蒙(こうむ)りたいという。併(しか)し場合が許さぬ、パアテルさんは未だ遠い遠い。道を誤(まちが)へて後戻りするやら何やらして甚い儉しい峠を超えると川がある、川の中に馬が遊んで居る。高浜の町は葡萄(ぶどう)で掩(おお)はれて居る、家毎に棚がある、棚なき家は家根に葡(は)はす、それを見て南の海の島らしい感じがした。豆を豆殻より離さむた槌もて莚(むしろ)を打つ子がある。三生は橋に凭(もた)れて暮れゆく雲を見る、二生は富岡に倣って駐在所を訪うたが留守だ、昔の大庄屋の家へ出かけ天草の乱の孝証中である、此処(ここ)は面白い、宿らうというH生の提議もパアテルさんには敵(かな)はん、H生は詩を作る。 五足の靴は驚いた。東京を出て、汽車に乗せられ、唯(ただ)僅(わずか)に領巾振山(ひれふるやま)で土の香を嗅(か)いだのみで、今日まで日を暮したのであった、初めて御役に立って嬉しいが、嬉しすぎて少し腹の皮を擦りむいた、いい加減に御免蒙(こうむ)りたいという。併(しか)し場合が許さぬ、パアテルさんは未だ遠い遠い。道を誤(まちが)へて後戻りするやら何やらして甚い儉しい峠を超えると川がある、川の中に馬が遊んで居る。高浜の町は葡萄(ぶどう)で掩(おお)はれて居る、家毎に棚がある、棚なき家は家根に葡(は)はす、それを見て南の海の島らしい感じがした。豆を豆殻より離さむた槌もて莚(むしろ)を打つ子がある。三生は橋に凭(もた)れて暮れゆく雲を見る、二生は富岡に倣って駐在所を訪うたが留守だ、昔の大庄屋の家へ出かけ天草の乱の孝証中である、此処(ここ)は面白い、宿らうというH生の提議もパアテルさんには敵(かな)はん、H生は詩を作る。
|
大江村 (八月二十二日)
  昨日の疲労(つかれ)で今朝は飽くまで寝て、夫れから此(この)地の天主教会を訪ねに出掛けた。所謂「御堂」はやや小高い所に在って、土地の人が親しげに「パアテルさん、パアテルさん」と呼ぶ敬虔なる仏蘭西(ふらんす)の宣教師が唯一人、飯炊男の「茂助(もをすけ)」と共に棲んでゐるのである。案内を乞ふと「パアテルさん」が出て来て慇懃(いんぎん)に予等を迎えた。「パアテルさん」はもう十五年も此(この)村にゐるさうで天草言葉が却々(なかなか)巧い。茂助善(よ)か水を汲んで来なしやれ。」と飯炊男に水を汲んで来させ、それから「上にお上がりまっせ」と懇(ねんご)ろに勧められた。又予等が乞ふに任せて、昔の信徒が秘蔵した聖像を彫むだ小形のメダル、十字架の類を見せて呉れた。夫れに附いてゐた説明の札には、「このさんたくるすは、三百年まへより大江村のきりしたんのうちに、忍びかくして守りつたへたる貴きみくるすなり。これは野中に見出でたり。」云々と書いてあった。此(この)種類のものは上野の博物館にあったやうに覚えてゐるが、却々(なかなか)面白い意匠のものがある。 昨日の疲労(つかれ)で今朝は飽くまで寝て、夫れから此(この)地の天主教会を訪ねに出掛けた。所謂「御堂」はやや小高い所に在って、土地の人が親しげに「パアテルさん、パアテルさん」と呼ぶ敬虔なる仏蘭西(ふらんす)の宣教師が唯一人、飯炊男の「茂助(もをすけ)」と共に棲んでゐるのである。案内を乞ふと「パアテルさん」が出て来て慇懃(いんぎん)に予等を迎えた。「パアテルさん」はもう十五年も此(この)村にゐるさうで天草言葉が却々(なかなか)巧い。茂助善(よ)か水を汲んで来なしやれ。」と飯炊男に水を汲んで来させ、それから「上にお上がりまっせ」と懇(ねんご)ろに勧められた。又予等が乞ふに任せて、昔の信徒が秘蔵した聖像を彫むだ小形のメダル、十字架の類を見せて呉れた。夫れに附いてゐた説明の札には、「このさんたくるすは、三百年まへより大江村のきりしたんのうちに、忍びかくして守りつたへたる貴きみくるすなり。これは野中に見出でたり。」云々と書いてあった。此(この)種類のものは上野の博物館にあったやうに覚えてゐるが、却々(なかなか)面白い意匠のものがある。「パアテルさん」は其(その)他いろいろのことを教へて呉れた。此(この)村は昔は天主教徒の最も多かった所で、島原の乱の後は、大抵の家は幕府から踏絵の「二度踏」を命じられたところだ。併(しか)し之で以て大抵の人は「転んで」仕舞って、唯この山上の二三十の家のみが、依然として今に至るまで堅く「ディウス」の教へを守ってゐるさうである。是等の人は今尚十字架、聖像の類を秘蔵して容易に人に示さぬ。或は深く柱や棟木の内に封じ込んでゐるものもあるさうだ。それで信者は信者同士でなければ結婚せぬ。縦(よ)し信者以外のものと結婚するとしても、それは一度信者にした上でなければならぬ。いや、今は転んで仏教徒になってゐるものでも家の子の出来た時には洗礼をさせ、又死んだ時にも、表面は一応仏式を採るが、其(その)後更めて密かに旧教の儀式を行ふさうだ、棺も寝棺で、内服装も当時の信徒の風に従ふのださうだ。予等は又「パアテルさん」に導かれて礼拝堂を見た。万事瀟洒(しょうしゃ)として且つ整頓してゐるが、マリア像の後に、赤き旗に、「天使の皇后」「聖祖の皇后」と記されたのは、少々辟易せねばならぬ。併(しか)し此(この)教会に集る人々は、昔の、天草一揆時代の信徒ではなくて、此御堂建設後、二十七年の間に新に帰依したものである。それは、大江村に四百五十三人、それから此の「パアテルさん」が一週間交代でゆく崎津村に四百五十九人あるさうだ。尤も昔の信者の家々も教会に集りこそせざれ、一週一日の礼拝日は堅く守って、その日は肥料運搬等の汚れた仕事は一切為ない。所が何という間違か、それは日曜日ではなく、昔から土曜日ださうだ。 一体日本近世の歴史で最も興味あるものは、戦国の終、徳川の初期に於ける外国文明の影響の如き其(その)一であらう。此(この)時代の新しい纏った研究の尠(すくな)いのは遺憾である。殊に長崎、平戸、天草辺から入って来た日本化した外国語などは、殆んど注意されずに消えてゆくらしい。若し恁んなことを調べる積りで九州下りまで旅する人があったら屹度(きっと)失望するだらう。土地の故老、吏員などに質しても、彼等は惘然(もうぜん)として答ふる所を知らない。 余り「パアテルさん」のことに引絡(ひきから)まってゐるとまた一行の人から諧謔(かいぎゃく)詩などを書かれるから、今度は此(この)村の有様を記さう。非常に薩摩に似てゐるとK生は言った。兎に角辺鄙な所で、三面は山、一面は海、猫額大の平地には甘藷(かんしょ)が植ってゐる。之と麦飯とが此(この)地の住民の常食だ。此(この)朝H生が髭を剃りに出懸けて、不図昨夜山中で、巡査に遇ったことを話したら、それから夫れと問ひ詰められて、結局「貴方達ちゃあ、何しにそぎやん旅行(ある)きなはんな?」「そぎやん金どきやんして儲けて来なはったな?」と驚嘆せられて戻って来た。序だが、昨夜の賊といふのは金二十五円を詐欺して逃げたのださうだ。此(この)島に取っては稀有の大事件らしい。 天主教会を下って海浜の街を歩いた。夏の真昼だから可いものの、之が例の秋の夕暮ででもあったら、其(その)蕭条(しょうじょう)たる風物は木乃伊(みいら)にでもされて仕舞うだらう。宿は木賃同様だから頓と食ふべきものがない。所が幸ひ此(この)散歩の途で南瓜(たうなす)を見付けたから、之を購ふことにして価を聞いたが、主人は幾等(いくら)でも可いといふ。「南瓜(ぼうぶら)」なんか、此(この)村では売買しないさうだ。結局三銭出して掲げて帰った様は聊(いささ)か滑稽(こっけい)だった。 午後二時、牛深行の汽船に乗る。牛深には夕刻着いた。今津屋といふ宿屋に宿ったが、楼上から市街を瞰(み)ると、何れも屋根の棟が(水平ではなくて)多少上方に彎曲してゐる。屋根を越えては又薩摩の陸影が見る。 夜街を散歩して漁人(れふし)町の粉々たる異臭、はた暗い海浜を通って、終に土地の遊女町に出た。唯だ三軒のみで、暗き灯、疎なる垣、転(うた)た荒涼の感に堪へなかった。上の家は桔槹(はねつるべ)の音が聞こえて足元に蟋蟀(こほろぎ)が鳴くなどは真に寂しい。 |
海の上 (八月二十三日)
 不届な宿屋(にして回漕店を兼ねる家)である、朝三時の乗込といふに、丁度三時に起し、周章(あわ)てなければ間に合ひませんと言ふ。漱(くちそそ)ぐは勿論、顔洗ふ暇もない、大いにうろたへて昨日H生んの知ひとから貰った西瓜(すいか)を抱へて汽船ねに乗込んだ。船の灯が三つ四つ見え、ゆるやかに湖流るる夜の港を賞したいは山々だが、如何にも眠いので下へ潜(くぐ)って寝てしまった。眼を覚すと夜が明けて居る、一同円くなって西瓜を食った、その旨い事非常である。西瓜は日毎に二つ三つ食ふ、九州は何処へ行っても西瓜の無い所はない、最も旨いものも西瓜である、殊に天草と島原はその産地だ、余り食って揃って腹を悪くした日もあった。甲板へ出る、船は天草海峡を走って居る、美しい多くの島が青い霞の羅衣(うすもの)を被(かつ)いで寝て居る、柔らかな光が水面を撫でてゆらゆらと揺れる。島の間に褐色の帆が散らばってゐる、山のたたずまひ、静かな海の様子が瀬戸内海に似て然も大いに勝る所がある。静かな海を静かに走る船は山の眠りを覚すまいと気遣(きづか)ふ。 不届な宿屋(にして回漕店を兼ねる家)である、朝三時の乗込といふに、丁度三時に起し、周章(あわ)てなければ間に合ひませんと言ふ。漱(くちそそ)ぐは勿論、顔洗ふ暇もない、大いにうろたへて昨日H生んの知ひとから貰った西瓜(すいか)を抱へて汽船ねに乗込んだ。船の灯が三つ四つ見え、ゆるやかに湖流るる夜の港を賞したいは山々だが、如何にも眠いので下へ潜(くぐ)って寝てしまった。眼を覚すと夜が明けて居る、一同円くなって西瓜を食った、その旨い事非常である。西瓜は日毎に二つ三つ食ふ、九州は何処へ行っても西瓜の無い所はない、最も旨いものも西瓜である、殊に天草と島原はその産地だ、余り食って揃って腹を悪くした日もあった。甲板へ出る、船は天草海峡を走って居る、美しい多くの島が青い霞の羅衣(うすもの)を被(かつ)いで寝て居る、柔らかな光が水面を撫でてゆらゆらと揺れる。島の間に褐色の帆が散らばってゐる、山のたたずまひ、静かな海の様子が瀬戸内海に似て然も大いに勝る所がある。静かな海を静かに走る船は山の眠りを覚すまいと気遣(きづか)ふ。天草島の最南端を発し、最北端を乗り越して肥後国(ひごのくに)際崎(きはざき)に着いたのは午後二時である。今日一日は、海上に生活せんけりゃならんのである。故に昼飯も陸上では食はぬ、際崎の船着場に大阪流の船料理がある、そこへ上がった。厳しい暑さだ、海へとび込みたくなる、K生を残して皆飛び込んで泳いだ、島原行きの船を待つ間の一興である。五時に三角から島原へ船が出る。三角まで十町今日久し振に陸を歩くのである。三角は近年熊本の人が好んで海水浴に来る処であると言ふ、三々伍々、田舎者の癖に嫌に威張って歩いてゐる。三角から島原へ行く海路の景色は今日までに見た自然の内で最も美しいものであった。紺青の温泉(うんぜん)ヶ嶽(だけ)が西の方行く手に聳え、日はその上にかかる、空の色、海の色の刻々に移り行くを眺めて夢の様な心になる。日が沈む、海が紅(くれなゐ)に燃えた。島多き島原へ着いた、真黒な眉山(まゆやま)が港を脅かして居る、いい所だ。島原の港はK生の詩でその一斑が分らう。
九州人は原という字が下に来る地名を凡て「ばる」と云ふ。島原も「シマバル」だ。風俗の淫靡なことは有名なものだ。良家の処女と雖(いえど)も他国から来た旅客が所望すれば欣々として枕席(ちんせき)に待する、両親が進んで之を奨励する。他国人と一度関係を結ばぬ女は縁附が遅いと云ふ程だ。 |
有馬城跡 (八月二十四日)
| 翌日朝飯を終へてから有馬城の故趾(あと)を観にゆく。島原の市街は存外に大きく、較(やや)都会の観を呈している。街の両側には清水が流れて川底が見え透く程澄んでゐるが、之が飲料水だと聞くと折角(せっかく)の快感が害はれる。川の中、店の前、車の上、全町到る所に西瓜(すいか)の多いのには驚かざるを得ぬ。 有馬城は可也大きかつたらしい。旧記には原城、丙城(ひのえじゃう)の二箇所に分れてゐたやうに書いてある。今城跡は荒れて悉く桑畑に成つてゐる。畠の中には随所に石垣が残つて、例の不恰好な中学校、小学校、監獄分監などが其(その)間に立つてゐる。城の石垣には一面に灌木が生ひ繁つて、濠(ほり)には蓮の花が藤色の台湾藻の花と雑つてゐる。多くは水涸れて里芋が植ゑてある。 此(この)城を見るものは、誰でも第一に天草四郎のことを想起すに違ひない。こゝは彼が最後に拠つて終に滅んだ所である。殊に其戦歿の時が十七才であると聞いては、何故ともなく一種悲壮の感に打たれる。此(この)一揆の起因は兎に角、之が盟主となつた少年彼の動機、其(その)心理等に至つては、旧記の載する所甚(はなは)だ尠(すくな)く、却つて後人の自由なる忖度(そんたく)の余地を残してある。自分は天草四郎の事蹟には成心(せいしん)を持てゐる。始めは唯想像に過ぎ中つたが、今は必然さうなくてはならなかつた事実の様に思はれて来た自分は天草四郎を一の天才と見るに躊躇(ちゅうちょ)せぬ。そして彼は又其(その)時代の精神に触れて……否現時吾等が感じてゐる様な近世的の鬱悶を持ってゐたに違ひないと思ふ。島原軍中話といふ本には「一揆の大将は天草甚兵衛が子益田四郎時貞といふものなり。幼少より才智人に勝れ、苟且(かりそめ)の遊戯にも兎角弓矢を手挾み、木太刀を取りて人に迫合ふことを好む。後習学の功を積まずして才覚双(ならび)なし、切支丹に深く立入云々」と書いてある。当時九州西部の切支丹の徒は幕府の迫害が烈しくて、廿六年前の夢のやうな識言(しんげん)「当年より廿六年目にあたり善人一人可出生(しゅっしょうすべく)、其(その)者幼(いとけ)なくして諸学を極め天にしるく顕る可し、枯木にも花咲き、山野に旗を立て諸人の首にくるすを立つ可し。東西雲の焼くること近々ある可し。「ディウス」を尊ぶ時至る可きなり。云々」と信じて、何物をか期待すること、昔の猶太(ゆだや)民のやうであった。時に森宗意軒(いけん)、蘆塚(あしづか)仲兵衛、松島伴兵衛、会津元察(げんさつ)などの面々、嘘か真か、策略か、信仰か、集ひ群りて四郎と天草の民とを煽動した。一方には長崎、平戸の辺から駸々(わんわん)と外国文明が入つて来て漂流者の話、美はしき南蛮国の磁器などは或は此(この)少年の多感なる耳目に詩的憧憬を喚起したかも知れない。女は伽羅(きゃら)の油に髪を結という天竺、はた碧眼の美丈夫がそう皂縵くえん(そうまんくえん)に以たる衣を着くるといふ、入船出船の阿蘭陀の都に此(この)世の幸を求めに行かうか。此の天下の変に乗じて男一代の名を成さうかはた荘厳なる金十字に跪いて彼の世の栄光を味はうか、是等の諸々の妖魔(でもん)は群(つど)ひ来つて彼の身辺を囲繞した。併(しか)し彼は最後に誇らしき天命に従つて天草の蒼民の心を救はうと決心した。それから富岡、本渡海峡の辺を転戦して、終わりに此(この)有馬城に拠つた。寒島の一少年兵を動かすこと、三万七千余人、一世の人心を震駭(しんがい)て天下ために騒然、幕府色を失ふ。時に九州諸侯の兵来り囲むもの漸く多く、翌寛永十五年二月廿八日、彼は終に討死したのである。 自分は僅少(わずか)な史的智識を基にして、此(この)昔を忘れ果てたやうな有馬城趾に色々な旧き姿、象(かたち)を並べて見た。併(しか)し漸く中央に登らうとする土用の太陽は恣に其(その)黄金の矢を投げ注ぐので、人間生活の基本なる「現在の需要」に随つて、懶(ものう)い足を又西瓜(すいか)の多い多い街に運ばねばならなかつた。 |
長洲 (八月二十五日)
| 爺さんが漕ぐ船の脚は遅い。正午、宿屋の裏から直ぐに乗つて、日本形の船の間を潜(くぐ)り抜けて、肥後国長洲行の汽船に乗つた、此(この)度の旅中に出会つた汽船の中で最も小さなものだ、これで有明の海を渡るのかと思へば、少し心細く思はれる。鯣(するめ)、梨子(なし)、焼酎等を売る女があつて「買はせんかな、買はつせんかな」と叫びながら櫓を操る。暫時して船は動き出したが、折柄舷側で佇むで居た口髭の濃い運転士は「源がまたもどらんぞ」と云って、船を其儘(そのまま)漂はさした若い水夫は、猶(なお)島原の浮かれ女が西瓜(すいか)くさい匂に酔つて、飽かぬ思に耽つて居るであらう。 源が帰つて船が出る。汽笛は此の若い水夫が、離別に流した涙を嘲(あざ)けるやうに響いて夏の真昼時ではあるが、恋の港の船出にさすがに悲哀の情趣がある。見れば甲板の隅の方で、源は船長の前に立った儘(まま)、悲しげにうなだれて居た。 物寂し相な、白色の燈台を左にして、船は緩やかに駛つていく。沖には千噸余の汽船が一隻碇泊(ていはく)して居て、海には浪の躍(おど)る日である。島原の港町が次第に隠れて、島原の城下町が次第に現はれて来る。其(その)街の尽きる辺から、広く青々とした裾野となって、高く仰げば温泉ヶ嶽は、大いなる母の如く聳えて居る。山は避暑の西洋人で一杯だと聞いて登らなかつたのが残念だ。船の上は人が満ちて寝る事も出来ぬ。機関に続く一室の屋根に腰を懸けて、乗合の人を見ていると却々(なかなか)面白い。前部には赤襟飾(ねくたい)、赤リボン吊、赤襪(あかたび)の生若い男が居て、女の写真を眺めて居る。後部には、手織綿の単衣を着た丁髷(ちょんまげ)の老爺が居て、茫然(ぼんやり)遠方の雲を眺めて居る。此(この)二人の間には、長い過渡の時代が挾まつている。船は百年の時を乗せて駛つてゆく。 渋茶を飲みながら不味(まず)い菓子を食つて居るうちに、向ふの岸が漸々(だんだん)明かになって、黄色の洲が見え出した。大牟田の辺から、黒い煙が盛に立騰(のぼ)る。炭礦と築港の産物であらう。其(その)煙の消えて行く空には、鼠色の雲が一面に群がつて、微かに雷鳴の響が聴える。 長州は其(その)名の如く遠浅の海である。満潮の時には、辛うじて岸近くに波が砕けるが、干潮の時には、数町の間黒い海の底が露はれて、貝の殻や小石が散在する。今丁度引潮の際で、五丈ばかりの石垣が高く現はれて、牡蠣(かき)が白く附いて居る。此(この)堤防の中に横たはつた小舟は、恰(あたか)も時代から取残された哀れな人のやうに、砂の上に座して居る。此(この)堤防の上には、小さな見すぼらしい燈台が立って居る。 汽船は陸から十町程離れて停まったので、艀船(はしけ)に乗り移つて暫らく行くと、艀船はまた陸から五町程離れて、舟子は其(その)手の棹(さお)を捨てる。と見れば驚いた、岸の方から三四十台の人力車が、入乱れながら海の中をざぶざぶと進んで来る、車夫は水中に股を没して、何か声高に饒舌(しゃべ)りながら、悠々と車を曳く。其(その)間に交わつて兵士が歩いて来たと思ったのは、滑稽(こっけい)にも田舎廻りの音楽隊の連中で、カーキ色のズボンを捲(まく)って、太鼓を荷ったり、太鼓を抱へたりして水中を渉つては艀船に近づき難いに驚いて居る。 そのうち艀船の両側に人力車が簇(むら)がつて押寄せる。客が争って蹴込に飛込むと梶棒は忽(たちま)ち動き出す。車は海の中を走つて行く。車の輪の心棒を隠す位の深さで、まるで橇(そり)が氷の上を滑ってゆくやうに、車は水の面を走つて行く。乗つて居る者の心地は世に例なき喜ばしさである。人は皆微笑して居る間に、三四十台の車は、厳(いか)めしい姿をして波打際に見張つて居る巡査の前を過ぎて殆ど同時に陸へ馳(は)せ上つた。 |
熊本 (八月二十六日)
| 長州から汽車に乗つた時、驟雨(しゅうう)が我々の上を過ぎた。植木の停車場(すてーしょん)では餅を売る、其(その)呼声「もち」では無くつて、唯単に「も」である。 上熊本の改札口を出て、今迄渇して居た東京の新聞を求めたけれども、見附からなかつたので、直ぐに人力車を走らせた。坂の上から下の市街を展望すると、まるで森林のやうである。が、巨細に見ると、瓦が見えて来る。「あゝ、熊本は此(この)数おほい樹の蔭に隠れて居るのだな。」と思ひながら、彼方の空を眺めると、夕暮れの雲が美くしく漂つて居て、いたく郷愁を誘はれる。 旦那方阿蘇へ御登りなら、好い宿屋へ案内すると云ふ車夫の言葉を容易く信じて、導くがまゝに幾つか道を曲ると、何屋とか云ふ古ぼけた宿屋の黒い門の中へ引きこむだ。髪を振り乱して、白い歯を現はした古女房が飛び出して来て、裏の方へ廻れと云ふ。玄関の破障子を横に見て、周章(あわ)てゝ鼠が逃込むだ台所口を通ると、懶(もの)うげな姿をして、背の低い娘が皿を洗つて居る。余り穢(きたな)いと口には出さぬが、黙々の裡に皆の心は合して、庭の方へ出ると、先づH生が、「こゝは止めませう」と口を切る。客が何処の室でも寝そべつて居て、何となく心持が悪い。「今二階を明けます。」といふ女の声を後にして、五足の靴を踏み鳴らしながら、勢よく裏門へ通り抜ける。若し此(この)宿屋に口があったならば、大きく開いた儘(まま)、長く閉ぢる事が出来なかつたであらう。 通りに出ると柳の生えた街である。文房具屋にダンテの石膏像があり、本屋に美しい洋書のあるところ、稍(やや)都めいて居るが、猶(なお)野臭あるを免かれぬ、研屋(とぎや)旅館の支店で服の埃(ほこり)を払つて、塵(ちり)だらけの帽子を床の上に投げ出した。 其(その)夜知れる人を訪(と)ひに住つたK生を除いて他の四人は唯徒(やた)らに街をさまよひ歩いた。白楊の並木のある道を過ぎて、兵営の前に出る。殺風景な軍営、没趣味な兵舎、これが此(この)処のみでなく城の上まで占領して居る喇叭(らっぱ)の響には哀味があるが、カーキ色の服には詩趣が無い。かゝる物を置くのは、どこかの曠野(あらの)がいゝだらう。噂に聞けば京都の紫野に兵営が出来るさうであるが、言語道断の事だ。こんな事を考へながら、名も知らぬ石橋を渡らうとした時、M生は突然「実に長崎に似て居るなあ。」と叫んだ。多くの氷水の露店が並んで居る辺、川の面に夕暮の残光が落ちかゝつて居る辺、洋館めいた家が立って居る辺、一寸髣髴(ほうふつ)として其の面影を忍ぶ事が出来る。長崎、長崎、あの慕かしい土地を何故一日で離れたらう。顧みて云ひ知らず残り惜しい。 知らぬ街の知らぬ路に迷って、ゆくりなくも二本木という強慾の巷(ちまた)に出る、白川の岸を辿(たど)りて帰らうとしたが、余りに足が疲れたのと路が分りかねるのとで、辻車を呼んで飛乗つた。夜風は思ひの外に涼し。 其(その)夜心の中で、かう云ふ断言を下した。「熊本は大いなる村落である。」と。K生云(いわ)く。西郷は彼の精鋭の太兵を率ゐながら鳥(からす)勢の百姓兵に此処(ここ)で負けた。 |
阿蘇登山 (八月二十七日)
噴火口 (八月二十八日)
| 第二日は垂玉の温泉から噴火口を見に登つた。此(この)路は殆ど二里許り、別に珍しいものも無かつたが、蒼茫たる高原に馬と牛とが自由に駆け廻つてゐる様は快い眺めであった。路は分りよいさうだが予等は念の為め仮に「六蔵」と名付けた案内者を頼んだ。此(この)六蔵先生には後に酷(ひど)い目に合されたが、登りは先々無事で、千里が浜を通つて阿蘇本社の所在地に出、そこの茶店で中食して後、終に絶頂に達した。 まだ噴火口の見えないうちから、既に褐色の煙は濛々(もうもう)と空を横ぎつて、為めに日の色は紫で、砂は気味悪い黄色を呈してゐた。火口に近くに随つて硫黄の香は犇々(ひしひし)と逼つてくる。噴火口が見えるや否や、予等が心は猛獣の如くに荒くなつた。口を閉して皆黙々として驚駭(きょうがい)の目を瞠るのである。底を知らぬ不可思議なる大きな壺の口からは、灰色の煙がもくもくと洶(わ)き、渦き、廻り、淀んで、空高く斜めに流れてゆく。其(その)様が如何(いか)にも自覚と目的とが有るやうである。固(もと)より轟々(ごうごう)たる物音は分秒の休みなく喚(おめ)いてゐる、併(しか)し惘然(もうぜん)たる凝視の間に予等は稍(やや)此(この)光景に狎れた。そして愈々(いよいよ)近く火口に歩み寄りて、終には巨石を此(この)内に投時て其(その)反応を検(あらた)めようとした。果は此(この)有名なる自然現象が、予等の驚嘆を喚起すること、大いなる工場に及ばないことを笑つたそして顧みると、三人の女学生めいた蓮葉(はすは)の女達は、亦火口を瞰望(かんぼう)してきやつきやつと笑つてゐる。平気なものだ。案内者六蔵は火口を目がけて七尺許りの金剛杖を投げる、と直ぐ高く噴出されて十五六間あなたへかちりと音がして落ちた。径五六寸の石は投込んでも底までは届かずに噴き出して了うさうだ。三人の女連は扇を投げ入れた、是は一寸面白いとK生が喜ぶ。昔の人は心から自然力に驚嘆した。火を崇(あが)め、山を祭つた。其(その)子孫なる今人は亦惰性的に自然を恐れてゐる。昔よりは衰へたが、併(しか)し今尚盛んな想像力で而かも現代の物質的文明から経験し得た諸々の写象を基として、外形的に巨大なものを自然から予期してゐる。そこで山に登る。登つてみれば、彼等の耳目に触れるものは、其(その)日常見聞する所のものから、さう大して優れてはゐない。そこで彼等は失望する。彼等は経験こそ多けれ、其(その)精神は昔の人程大きくないのだ。「崇高」は外に無くて、内に在る。昔の人は僅少(わずか)な自然動にでも、全心を燃やす可き大いなる火縄を得ることが出来たのだが、それが彼等には出来ないのだ。自分は山を下リ乍(なが)らつくづく現代と自分とを咀つた。そして変な情動から駈け出したら、石に躓いて、倒れて、したたか助骨を打つた。 此(この)山の新火山は去年六月の頃始めて生じたのだ、旧い方はそれから稍(やや)隔つた所にあつて其(その)底に熱湯を滾し、悠々と白気を吐く所は、恰ら名を成して隠退した老大家の観がある。再び嚮の茶店に戻つて休憩し、将た渇望を満足したりなどして、また案内者六蔵を先に立てゝ、千里ヶ浜を横里、来た方とは違つた路を採つて湯の谷温泉へ下り始めた。山腹に立つて、大なる外輪山脉を眺めると、世紀末の今人でも、大きい古典的な情緒と、聯想とを起さずにはゐられなゐ。比間に年寄りの夫婦が来て、道を知らぬから予等に随つて歩くのを許せといふ。そこで、漱石氏が「二百十日」式の、蓬々(ほうほう)たる茅生(かやふ)の間を歩むこと殆んど二時間許りであつた。此(この)山腹には、草といへば殆ど茅(かや)許(ばか)りだ。それも毎日降り積む霾の為めに下拙画工(へぼえかき)の雪中廬雁図(せっちゅうろがんず)の様に灰色にぼけている。所が一行の某生が気付いたところによると、この路は決して湯の谷の方向を指すものではない。「どんべん山」を中心として目指す所寄りは九十度以上も余計に廻つてゐる。路は阿蘇村の方に行く矢うである。そこで予等は飢ゑて荒野に彷徨(さまよ)ひ漂浪者が旅人に出遇つたやうに、此(この)愚かな案内者を責めた。案内者は恐縮して兎のやうに路なき所を駆け回つて路を探す。予等は益益困つた。恁(こ)んな風で予等に続いた老夫婦にまで飛んだ迷惑を掛けて、やつと湯の谷行の道を発見したときは、山を下り始めてから殆んど三時間半も過ぎた後であつた。湯の谷で休んで暫し憤懣の気を緩くしたんのち、相議して、案内者には二十五銭だけ賃銀をやることにした。実際此(この)辺では過分な報酬なのか、それとも恐縮んに堪へなかつたのか「これぢゃあ多かありまッせむか」といひ乍(なが)ら手を出して、金を受取り、又兎の様に飄然(ひょうぜん)と去つて仕舞つた。 此(この)日午後の暑気は亦猛烈を極めたものだつた。予感は談笑しながら無益にも多大の期望を抱きつつ、夕の飯に馬肉を食はせられやうとは露しらずに、橡の木温泉に疲れた足を引摺つた。湯宿は一軒切りだ、而も入湯の客は百二十人も居る。座敷が無いので散髪宅と駄菓子屋とを兼ねた向ひの家の穢(きたな)い二階に泊まることゝ成つた。 |
画津湖 (八月二十九日)
 阿蘇の栃の木温泉から復(また)六時間炎天の悪路をガタ馬車に揺られ乍(なが)ら熊本に帰つて来た。此(この)馬車に乗ると大抵の人は五分位発熱するさうだ。K生は昨夜来風邪の気味で発熱して居る上此の馬車に揺られたから、体熱を検すると三十八度ある。甚(はなは)だ大儀なので早く服薬して寝ようと思つて居ると、珍らしや旧友松村竜起氏が訪ねて来る。氏は今こそ熊本市隋一の靴製造業松村組の主人であるが、十二三年前は予と共に韓国の学部に就職し京城の乙未(おつび)義塾に教鞭(きょうべん)を執つた人だ。当年の事が色々目に浮ぶ、殊に韓国の近状と思ひ比べて今昔の感が深い。氏は今夕予の為めに水前寺畔の画津湖に船を泛べる準備がしてある、既に先発して待つて居る者もあると云ふ。厚意辞し難く発熱を犯して人車を聯(つら)ね、駛(は)すること一里弱、薄暮水前寺に着いた。水前寺はもと藩主細川氏の別墅(べっしょ)であつたが、今は一私人の有に帰して居る。之を市有として公園となす計画もあるさうだ。陰暦七夕の月明りで能くは見えぬが瀟洒(しょうしゃ)幽静、一寸岡山の後楽園を小さくした趣がある。併(しか)し彼の旭川の水を引いた池は格別美しくも無いが、この水は、池中到処に清冽(せいれつ)の泉が噴き出すのであるから清々(すがすが)しい。水前寺の後に画津湖がある。水前寺の水が落ちて大小二つの湖水と成つたものだ。松村氏は予を湖畔の旗亭勢舞水楼(せんすいろう)に案内した。既に座に在る者九州日々新聞社の上田桔梗、九州めざまし新聞社の相賀重蔵、九州朝日新聞社の城三十郎、九州実業新聞社の池本迂巻、雑誌「尚美」記者河瀬紫草の五氏、皆生面の人々である。上田氏から社長小早川秀雄氏が予に寄せた一書を受取る。氏も亦松村君と同じく韓国に於る旧知だ、氏が三角港に急行する為め今日の祝宴にまのあたり久濶を叙し得ぬことを遺憾に思ふとあるのは、予もまた言はむと欲する所だ。 阿蘇の栃の木温泉から復(また)六時間炎天の悪路をガタ馬車に揺られ乍(なが)ら熊本に帰つて来た。此(この)馬車に乗ると大抵の人は五分位発熱するさうだ。K生は昨夜来風邪の気味で発熱して居る上此の馬車に揺られたから、体熱を検すると三十八度ある。甚(はなは)だ大儀なので早く服薬して寝ようと思つて居ると、珍らしや旧友松村竜起氏が訪ねて来る。氏は今こそ熊本市隋一の靴製造業松村組の主人であるが、十二三年前は予と共に韓国の学部に就職し京城の乙未(おつび)義塾に教鞭(きょうべん)を執つた人だ。当年の事が色々目に浮ぶ、殊に韓国の近状と思ひ比べて今昔の感が深い。氏は今夕予の為めに水前寺畔の画津湖に船を泛べる準備がしてある、既に先発して待つて居る者もあると云ふ。厚意辞し難く発熱を犯して人車を聯(つら)ね、駛(は)すること一里弱、薄暮水前寺に着いた。水前寺はもと藩主細川氏の別墅(べっしょ)であつたが、今は一私人の有に帰して居る。之を市有として公園となす計画もあるさうだ。陰暦七夕の月明りで能くは見えぬが瀟洒(しょうしゃ)幽静、一寸岡山の後楽園を小さくした趣がある。併(しか)し彼の旭川の水を引いた池は格別美しくも無いが、この水は、池中到処に清冽(せいれつ)の泉が噴き出すのであるから清々(すがすが)しい。水前寺の後に画津湖がある。水前寺の水が落ちて大小二つの湖水と成つたものだ。松村氏は予を湖畔の旗亭勢舞水楼(せんすいろう)に案内した。既に座に在る者九州日々新聞社の上田桔梗、九州めざまし新聞社の相賀重蔵、九州朝日新聞社の城三十郎、九州実業新聞社の池本迂巻、雑誌「尚美」記者河瀬紫草の五氏、皆生面の人々である。上田氏から社長小早川秀雄氏が予に寄せた一書を受取る。氏も亦松村君と同じく韓国に於る旧知だ、氏が三角港に急行する為め今日の祝宴にまのあたり久濶を叙し得ぬことを遺憾に思ふとあるのは、予もまた言はむと欲する所だ。一酌の後庭に下りる。庭の後は直ぐ画津湖だ。紅提灯(あかちょうちん)を吊した屋形船が一艘(そう)早くから用意が出来て居る。一同乗る。船は湖心に向つて徐ろに進む。四方の岸は薄暗い、静かだ、静かだ、そよとの音も無い。満天の星が澄徹の水にじつと動くこと無く映る。螢がたわたわと飛ぶ。熊本の市内の暑苦しさに比べると全く別世界だ、人々は「あゝ涼しい」と云ふ言葉を忘れて居る。此(この)時其々の二妓は絃を按じて特に肥後の古い土謡を唄ひ出した。今其(その)一二を録さう。括狐の中の文字は舟中諸氏の註解だ。 おてもやん(人名)あんた此(この)頃嫁入したでは無いかいな。(以上問語、以下答)嫁入したこたしたばッてん(したけれど)ごんじやどんが(夫が)ぐぢやッぺぢやるけん(疱面なる故)まあだ盃きせんだッた。村役、鳶役(消防夫)肝煎どん、あんふとたちの居らすけんで(彼人達の居られるから)後はどうなッときやあなろたい。(きやあは接頭語。後の始末は何とか成るであらう。以下の語は一転して景物に叙す)きやあばたまッさん曲らうたい。(川端街の方へ曲り行かむ)ぼうぶらどんたちや(南瓜どもは)尻ふッぱッて(尻を出して)花ざあかり花ざあかり。 一つ山越え、も一つ山越えて、わたしゃあんたに惚れとるばい、惚れとるばッてん(けれど)言はれんばい、村の若い衆が張番しとらすけん。(村の若い男が他村の男に我村の娘の子を奪はれまいと警戒して居る故に)追々彼岸も近まれば、くまんどん(熊本)の夜ぢよみよんみやありに、(聴聞参り即ち説教参りに)ゆるゆる話ばきやあ為うたい。(以下一転して女より男の容貌に焦れず、その男の豪著な風俗意気に感ずる旨を云ふ)男振には惚れんばな、煙草入の銀金具が夫が因縁たい(以下拍子)あかちやか、べッちゃか、ちやかちやかちや。 七日の日が西に落ちて更けてゆく夜の涼しさ骨身に沁む頃、船は勢舞水楼に引返した。 楼上では松村氏の韓国王妃そ落(そらく、天子の死去の意)当夜の懐旧談が初まる。大院君が深夜異邦の志士に護せられ王妃を刺さむとするに、悠悠冷水を引いて身を拭ひ、徐(しず)かに髪を結び、衣装を此か彼かと撰び改め、更に天地四方の神を拝し、祖宗を祀り、促して後漸く輿に乗る、此(この)間費すこと三時間。志士等もどかしがりて而せば、大事を挙ぐるに然か軽々なるべけむやと云ふ。之が為に予定の時間より五時間も遅れて、玉城の正門に達した頃は既に白々と夜が明けた・・・・・・・。 夫から加藤清正談や西南戦争談などがあつて、却々(なかなか)興は尽きぬが、十二時が鳴つたので一同車をつらねて熊本に帰つた。今日人に、六七年前俳句や歌を作つた渋川石人はどうしたと聞いたら、「東京朝日」に玄耳と云ふ名で文章を書いて居るのがその石人だと分つた。 |
|
| ところで、本文中の5人のイニシャルは誰を指すのか解りましたか?「B生は驚いて・・・」などの五足の靴のメンバーを表すアルファベットです。B(万里)、H(白秋)、I(勇)、K(寛)、M(杢太郎)と推測できるのでないでしょうか。それぞれの場面で誰がどんな行動をとったか考えながら読んでいけば、5人への興味も倍加しそうです。 |
| 本ページ作成あたっては、濱名志松先生の著書「五足の靴と熊本・天草」(国書刊行会発行)を利用させていただきました。「五足の靴と熊本・天草」には「五足の靴」全文をはじめ、関係者の方々の証言や関係資料などが多数まとめられています。「五足の靴」研究のバイブル的存在ではないかと思っています。一読をお薦めします。濱名先生には、本ページの発信を快く承諾していただき、感謝申し上げます。今後ともご指導の程よろしくお願い致します。 |
|---|
| 現在「五足の靴」一行が歩いた山道の一部が「文学遊歩道(下に案内図あり)」として整備されています。途中には展望所などがあり、当時と変わらない眺望が楽しめます。下の写真は天草町役場(当時)よりご提供いただいたものです。ありがとうございました。(2004/03/10) | |
 |
 |
| 遊歩道の入り口 | あまくさ荘上の展望所 |
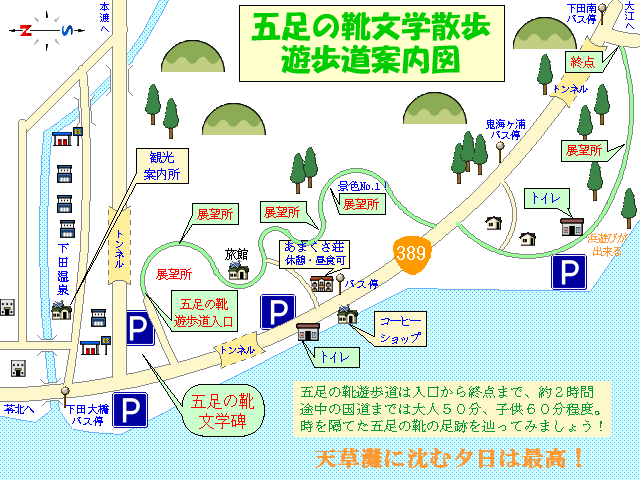
原文は文語体の難しい言葉や旧字体も多く、表記できずに新字体やひらがなを使ったり、勝手にふりがなを挿入したりしています。更には、私たちの誤記もあるかとも思います。お気づきの点等、ご指導いただければ助かります。間違い等が解り次第訂正して参ります。なお本文中の写真は、本サイトの他のページで利用しているものを適当に挿入したものです。
製作:熊本国府高等学校PC同好会(最終更新:2008/12/06)